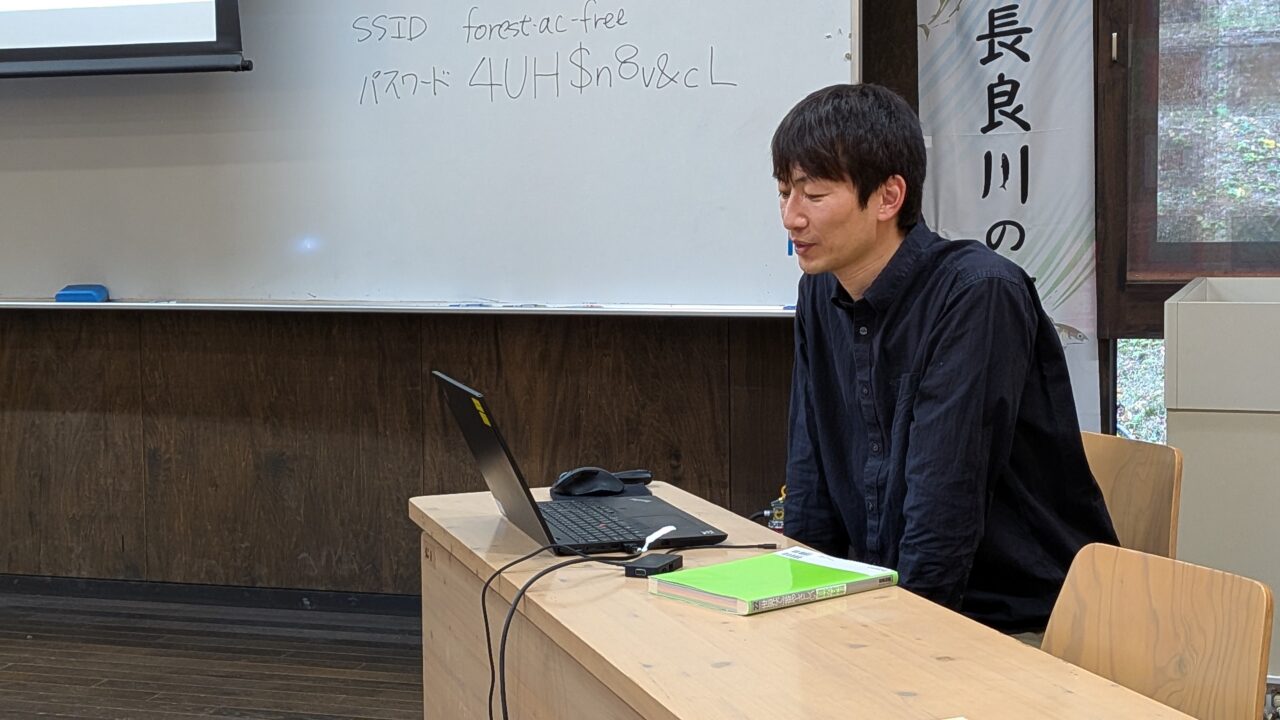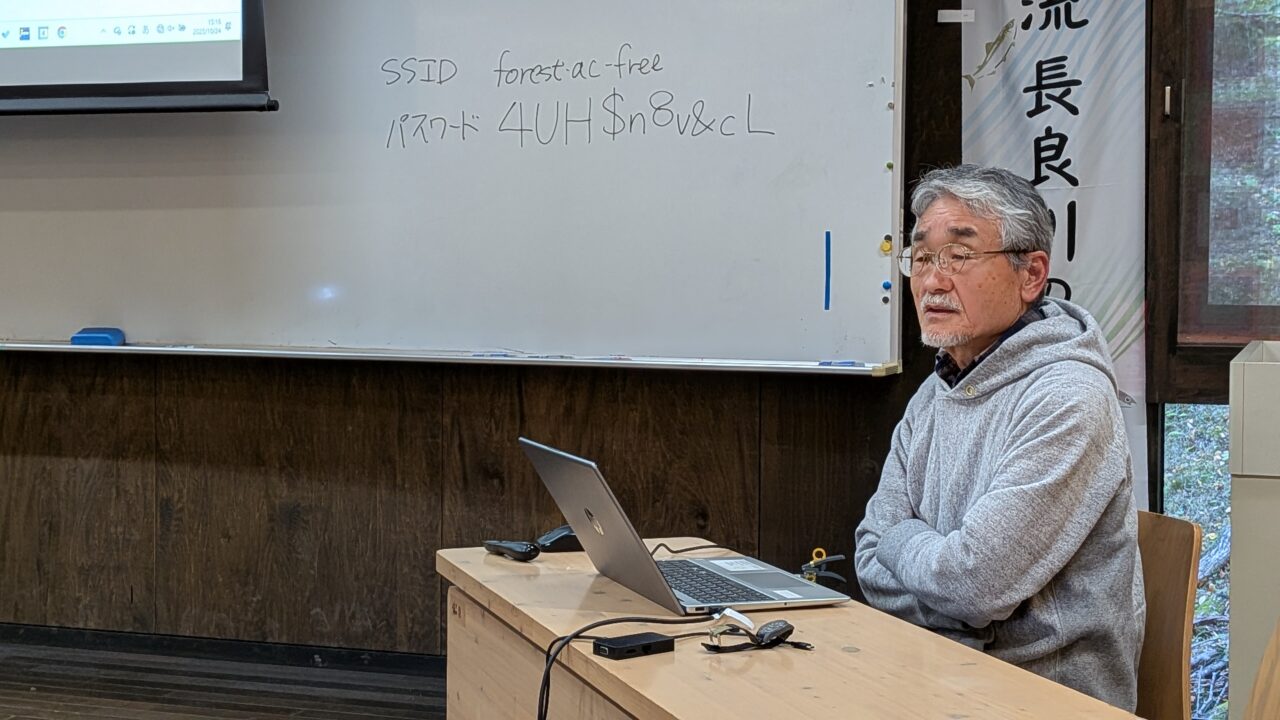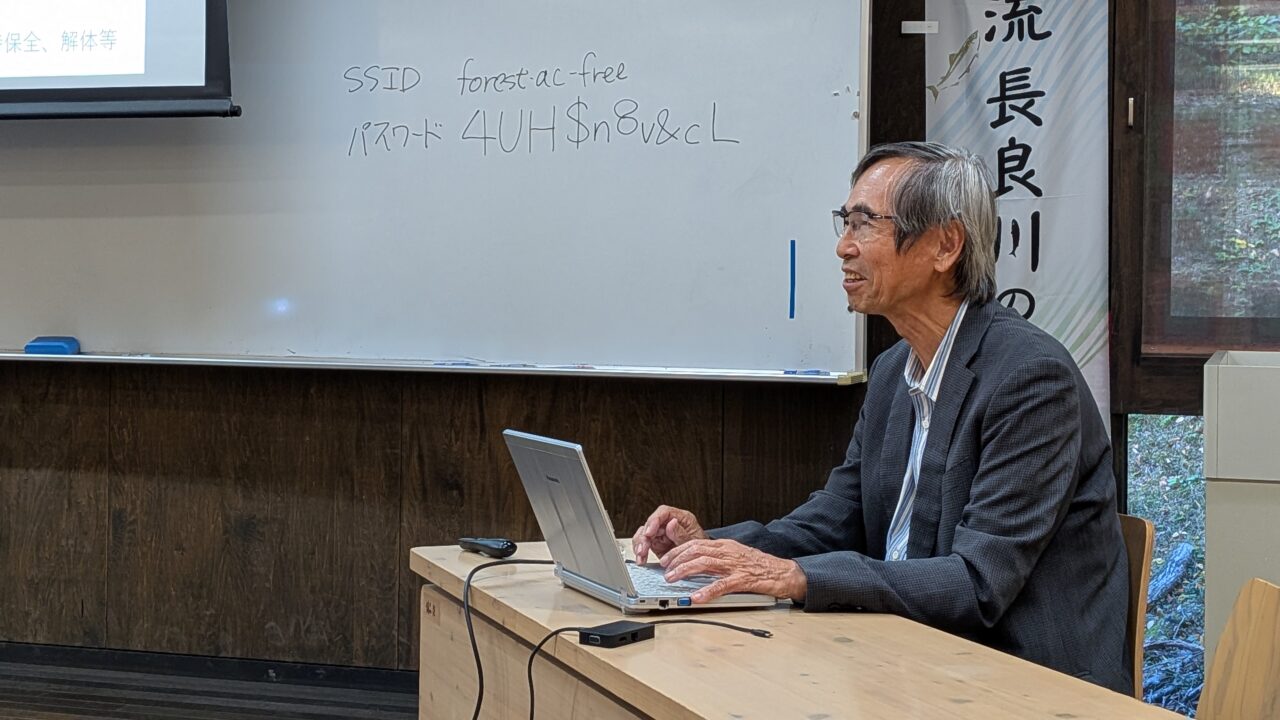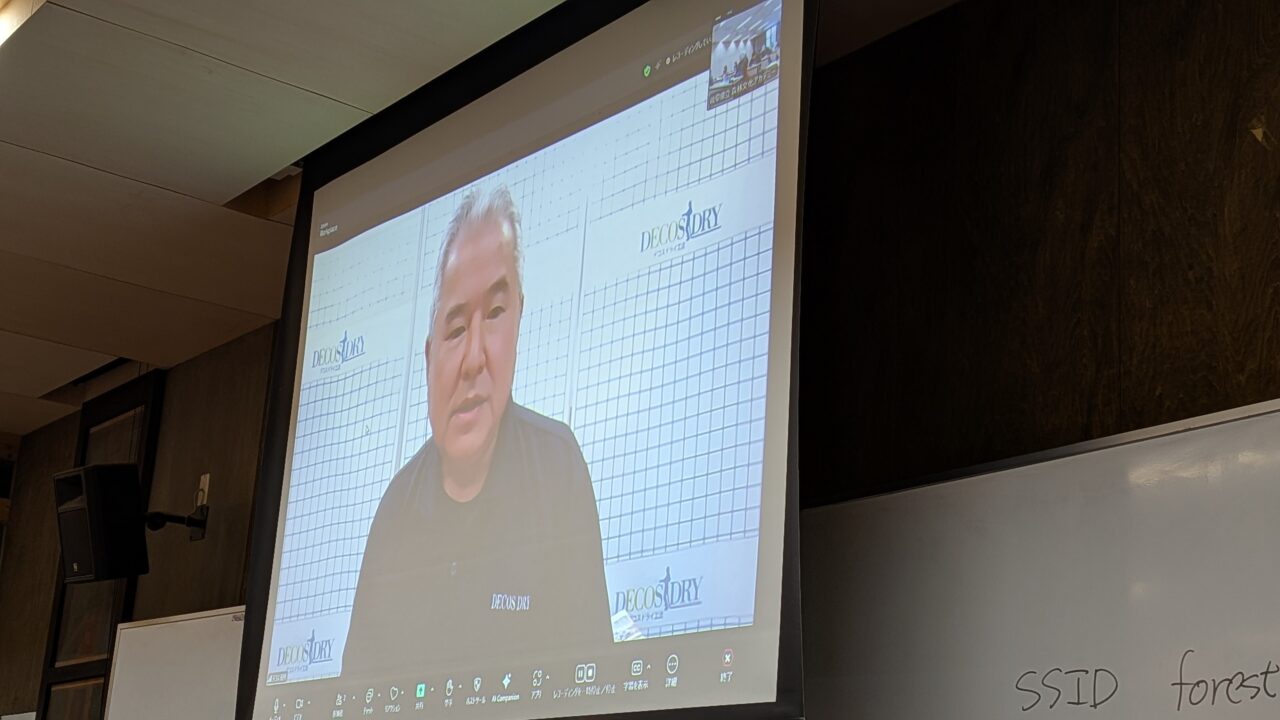第五回 バウビオローゲ(建築生物学の実践者)の集い ホールライフカーボンとバウビオロギー
バウビオロギーはドイツ発祥の総合学問で、名前の由来はBAU:建築、BIO:生命、LOGIE:学問ということで、建築生物学と訳し人を中心に据えたホリスティックな学問です。
このバウビオロギーの実践者、つまり人に寄りそう住まいや建築を作っている・広めている方をバウビオローゲと呼びます。
これまで、建築生物学の授業の一環でバウビオローゲ(建築生物学に実践者)の集いに学生も参加してきました。。
2019年 第一回 バウビオローゲの集い
2022年 第二回 バウビオローゲの集い
2023年 第三回 バウビオローゲの集い
2024年 第四回 バウビオローゲの集い
今回、第五回バウビオローゲの集い「ホールライフカーボンとバウビオロギー」は本学で開催しました。
九州から東北までのバウビオローゲの方々が全国から集まりました。
最初に、出席者の自己紹介(出身、普段の仕事、バウビオロギーとの出会い)から始まりました。建築関係の方だけでなく医療関係の方や、前職の多種多様な職種などバウビオロギーらしい多様な人が集まりました。
次に全国で活躍されているバウビオローゲの方の報告です。
最初は岩手県庁で家づくりにも関わられている阿部さんから「バウビオロギー住宅とアフォーダブル住宅」についての報告です。
バウビオロギーで大切にしている体を作る「食」、体を守る「衣」、その外皮のあたる「住」の大切さから始まりました。
次に住生活基本計画の最新情報では、人、もの、プレイヤーの大切さにフォーカスしています。
本題のバウビオロギーとアフォーダビリティでは、適正な価格で人間的な暮らしができる重要性が語られました。経済と健康は対立関係ではなく、アフォーダブルの量的、経済的な家づくりに加え、バウビオロギーの質的、生態学的に配慮された家づくりを目指すべきと、岩手県の方で活動されていました。
次に、埼玉で家づくりをされている落合さんから「埼玉で試行するバウビオロギーの家づくり」です。
ご自身で、合理性とバウビオロギーの思想を融合された部材を開発されている多彩な方です。
セルロースを吹き込んだプレファブ古パネル工法や、透湿遮熱ルーフィング、PP(プロピレン)のラス網、木製トリプルサッシ、木材を接着剤を使わず釘で接合したBSパネルなど、興味深い取り組みです。
次に今年度のバウビオローゲの集いのテーマ「ホールライフカーボンとバウビオロギー」に踏み込んでいきます。
ホールライフカーボンとは、建物の一生涯で排出される炭素のことです。
近年、ZEH、ZEBが一般的になり、運用時のエネルギーやCO2排出量(オペレーショナル・カーボン)はかなり削減されてきました。そうなると、建築時、改修時、解体・廃棄時などのエンボディドカーボンの削減が重要になってきます。つまり、ホールライフカーボンです。環境負荷を抑える素材の選定や改修しやすい建築工法など、総合的な視点が大切になってきました。
一方で、バウビオロギー的な居住環境の視点をどのように組み合わせていくのかが今回の狙いです。
そこで、ホールライフカーボンの中心で活動されている東京都市大学名誉教授の坊垣先生に「ホールライフカーボンの行方」の話をいただきました。
ホールライフカーボンの世界的な動向と、日本の対応、これからどう展開していくのかなど、なかなか聞けない最新情報を得ることができました。
日本で適切にホールライフカーボンを算定できる人の育成にも力を入れられています。
翌日は、参加者で「ホールライフカーボンとバウビオロギー」をテーマにディスカッションしようと、話題提供から始まりました。
最初は日本セルロース断熱施工協会事務局長の田所さんから「脱炭素時代に選ばれる断熱材」として、日本で初めてISO14025に準拠した断熱材デコスファイバーの環境製品宣言EPD(Environmental Product Declaration)の話など詳しく効くことができました。
バウビオロギーと相性のいい製品だけに質問が絶えず、大いに盛り上がりました。
次に、私、辻から「ホールライフカーボンの評価事例と課題」と題して、morinosのホールライフカーボン評価と現在の課題を整理しました。
ディスカッションの時間が限られてしまいましたが、参加者みんなからの感想をいただきました。
気候変動対策としてのカーボンの重要性とそれだけにとどまらないホリスティックな視点の大切さが共有されたと感じます。
バウビオロギー研究会代表の石川先生から最後の挨拶があり、本会が終わりました。
午後からは、morinosの森の案内人、川尻さんの森林体験プログラムが行われました。
山の神に向かう道中に木曾五木の説明や有用、毒性植物の解説など興味深い話の数々。贅沢な時間でした。
充実した2日間でした。