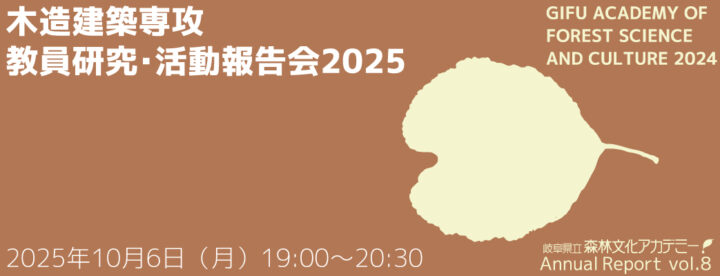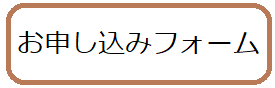アニュアルレポート2024発刊と木造建築専攻 教員研究・活動 報告会2025
アニュアルレポート2024が発刊されました。
主に教員の研究成果を取りまとめるアニュアルレポートも8号となり、研究成果が充実してきました。
ぜひご覧ください。
過去のアニュアルレポートはダウンロードページから見ることができます。
また、発刊を記念して「木造建築専攻 教員研究・活動 報告会2025」を開催します。
日時:令和7年10月6日(月)19:00~20:30
参加費:無料(定員先着30名、事前申込みが必要です)
詳しい内容はこちらから
以下にアニュアルレポートより、涌井学長の言葉を引用します。
学長のことば(アニュアルレポート2024より)
岐阜県立森林文化アカデミーは、我が国の教育体系の中でも特異な存在と自負している。多面的公益機能を有し、とりわけ昨今世界では、持続的未来を考える上で不可欠な存在として森林空間は更なる評価を受けている。地球環境問題への対処の二つの根幹的国際協約。気候変動ではCO₂の吸収源として、生物多様性条に於いてはまさに存在そのものが、プラネタリーバウンダリーへのリスクをカバーする存在として着目を集めている。
そうした森林並びに森林空間を主題に据え、その恵沢を維持・復元或いは更に高めるための健全な森林の撫育。木材の素材原木としての利用の範囲を拡大し、CO₂を封じ込めたまま人間生活に利便性をもたらす貴重な環境素材として利活用する建築・木工分野の構造並びに加工技術と意匠や用途開発。
そして健全な森林空間を維持するために欠かせない地域社会創り。森林を主役にした自然との応答関係の中に生まれる癒しや遊び、学びといった多岐な機能を供給する森林サービス産業等、多面的観点からアプローチし、その利用のルールや方法の探求などを包摂しつつ、森林を科学し体系化を進める中で、知識のみならず実体験そのものの演習を加えた学びを統合したキャンパス。それが「県立森林文化アカデミー」である。
学長としての教育哲学は一言で言えば、現場に存在する真理や真実を重視した、実践的な学び「現地現物主義」の言葉に収斂する。本学はまさにそれに相応しい教育環境と教職員の熱意があるとは言え本学が、県や森林産業界からの熱い支援を基にした優位性と特異性を誇ることが出来るからと言って、それに甘んじることがあってはならない。何故ならば、日を追うごとに我々の生存条件、地球の未来への余白が消える速度が増し、地球の大きさに比べれば極めて薄層且つデリケートな生物圏がもたらす「生態系サービス」の供給とその持続性が危ぶまれ、我々はある種の文明の大転換の狭間、所謂トランスフォーマティブ・チェンジ(社会的大変容)に置かれているからである。
確かに1992年以来、そうした未来を予兆し「生物多様性」と「気候変動」を基軸にした地球環境の健全化に対し、国際条約を以て対応してきたものの、経済成長至上主義とのせめぎ合いに敗れ目先の現実を優先し、我々並びに次世代の持続的未来への可能性の範囲の縮退を余儀なくされている。
「経済は成長しても、地球は成長せず、生態系サービスにも自ずと一定の容量がある」という原則は頭で理解されても実践にはつながっていない。
そうした中で着目されているのが、先に述べたCO2吸収能力などの気候変動抑制効果と多様な生態系を以て構成されている森林が果たす多岐な機能である。森林には木材や副産物の供給、そしてレクリエーション空間としての利用効用ばかりではなく、SDGsなど持続的未来を可能とする為の気候変動と生物多様性の両面に働く存在効用がある。
故に、そうした森林やその空間に纏わる専門家の必要性は高まるばかりである。とは言え、そうした分野の学びの場。つまり実践的教育機関の数は実に少ない。本学は図らずも全国からその独自性。わけても多彩な専門分野に亘る教官と、少数担当教育が評価され、多くの期待を集めている。これに応えようと、他者からの評価に耐えうる教育の質を維持発展させようと日々奮闘を続けている。
座学のみならず、危険性をも伴う現地現物のリアルな実践教育を少人数教育とはいえ、掲げた水準を下げずに、教育の体系化に勤しむ事は実際に担当教員とそれを支える事務局にかなりの緊張と負担感を伴う事となる。しかしそれが可能なのも、教職員のチームワークに、上級生も交え下級生を指導する事が当然とする本学の伝統的チームワーク教育が浸透していればこそ実現が出来ると思料している。
日常の教育に、常に新たなトピックを与えようとする知見の吸収。その上でフィールドから得た新たな発見を既往の知見と照応させ、独自の見解と知見のフロンティア化を惜しまない姿勢は、学の体系に基づく本学にとって、実に重要である。
とは言え多忙・多用な日常の教育。それに伴う雑務の狭間の時間に、気づきや発見を改めて体系の中に繰り込み、論文として報告し、他者の査読に供する設えを用意することはそう容易な事ではない。それでもそうした日常性を疎かにせず、本学の教員が、いつしかそうした積み上げが教育の基礎となり、より高い水準の教育と連動するとの確信が共有されていればこそ可能となる。そうした教育の水準の向上に資する研究活動への共通認識が生まれ、継続され、本アニュアルレポートが今年度もまた刊行できることは、学長として高く評価し、併せて最大のねぎらいと謝意を献じたい。
さらに言えば、本学教員のこうした姿勢と研究成果の一部は、学術領域を共にする研究者からも大いに評価され、全国の教育機関に共有化され、その一部が報道されるケースも表出しだしている。
日頃より本学を支えて頂いている機関や個人の皆様。そして関係分野から本学の教育研究に興味を抱いて頂いている皆様にご理解を頂く為に、敢えて本アニュアルレポートの継続的刊行を取り巻く状況について触れさせて頂いた。是非皆さまに於かれては、そうした本学の教員のひたむきな姿勢の成果。並びにそれを支える職員のひたむきな姿勢をご理解賜わり、益々のご理解の増進。そしてさらに厳しく学術の体系に照らしたご批判や、ご教導をも与えて頂ければ幸いである。
このレポートも2024年を以て8号となった。是非とも多くの方々に供覧を頂き、本学の教育とその背景を成す研究の両面に亘り、岐阜県立森林文化アカデミーに対するご支援を重ねて希う次第である。
岐阜県立森林文化アカデミー学長 涌井 史郎