卒業生が企画、在校生がゲスト!美濃市で教育とまちづくりを考えるワークショップ開催
2025年5月に美濃市地域おこし協力隊に就任した久野春奈(くの・はるな)さん。森林文化アカデミー エンジニア科21期生(2021年入学・2023年卒業)です。卒業後は企業勤務を経て、美濃市の地域おこし協力隊に応募。見事採用され、「森林教育コーディネーター」という新しい役割を美濃市につくるため、活動を始めています。
7月29日、久野さんが参加した島根県へのスタディツアーの報告会が、 美濃市のコワーキングスペース「WASITA MINO」で開催されました。

視察報告中の久野さん
久野さんが訪れた島根県・隠岐島前海士町は、離島でありながら高校魅力化など、「地方創生の一丁目一番地」として全国的に知られる地域です。
今回の訪問は、森林環境教育専攻の授業「教育のまちづくり」「コミュニティ・コミュニケーション」の連携したスタディツアー。アカデミー生に加えて、岐阜大の教員と学生、そして久野さんも参加して、様々視点で現地を捉えてきました。
視察報告を兼ねたワークショップには、美濃市民、行政、教育委員会、学校関係者、そしてアカデミーの学生・教員・卒業生など、定員を超える15名以上が参加。
久野さんからは、「始める」「挑戦する」が当たり前の文化づくりや、行政と民間のシームレスな連携、若者の就労機会の設計など、海士町で得た視座を共有されました。

島の入口から見える隠岐島前高校
そして、久野さんが隠岐島前への視察に惹かれた理由、それは
「レールから外れる選択をする若者たち」
地元の高校に行き、大学に行き、就職する・・・世間一般で中学生に期待される「レール」に疑問を持たなかった久野さん。しかし、隠岐島前高校や、「地域みらい留学」など、大人が言うレールとは違う選択ができるのはなぜか?
その疑問を深堀りするために、2人のアカデミー在校生とのトークセッションが続きます。
新しい進路を選択する10代のリアルとは
一人目は、エンジニア科1年の柳原彩音(やなぎはら・あやね)さん。
兵庫県出身で、「地域みらい留学」の制度を利用して、徳島県神山町の城西高校 神山校に進学しました。
この神山校、実は2023年に授業「教育のまちづくり」でうかがったところです!
柳原さんは、コロナ禍で緊急事態宣言が出された2020年は、中学2年生。
学校は閉鎖となり、学校というコミュニティとの分断が生まれたことで、それから不登校になったとのこと。
地元の高校に行く勇気が沸かなかったとき、教員であるお母さんが学校で「地域みらい留学」の情報を聞き、勧めてくれたのがきっかけとなったそうです。
高校時代を過ごした神山町は、「やったら、ええんちゃう」が合言葉。
神山校では、学校の活動でも、そして寮でも町の人と多く関わります。
いろいろなチャレンジをさせてもらえ、失敗もして、迷惑をかけ、後悔もあるけど、そのお陰で自分自身を知ることができた、と柳原さんは語りました。

進行の久野さん(写真右)と、エンジニア科1年・柳原さん(中央)、エンジニア科2年・駒田さん(写真左)
2人目は、エンジニア科2年の駒田一葉(こまだ・かずは)さん。愛知県出身です。
柳原さんの一つ上の駒田さんは、中学3年生、高校受験の年に緊急事態宣言を体験します。
コロナ禍の影響は高校選択、そして迎えた高校での高校生活に及びます。
思い描いたような高校生活ができず、勉強のみの生活が続いていくことに疑問を持つようになったそうです。
「学校がなくなったら、自分には何が残るんだろう?」
そんなとき、農的な暮らしをしている旅人と出会い、これまで知らなかった世界が開かれていきました。
高3の夏、学校を辞める選択をして、ネットの高校に編入。通信制の学校に通いながら様々な人々と出会いました。
学校を辞める、大人が考えるレールから外れることを決意したとき、親御さんと分かりあえないことに最も悩んだそうです。そんなとき、通っていた恵那市のハム工房のオーナーが親を連れてくることを提案。実際に場所を訪れ、人と会うことで、親御さんも少しずつ少しずつ、駒田さんの見ている世界、そして将来の思いを理解されていったそうです。
高校卒業後の進学をあまり考えていなかった駒田さんでしたが、高校時代の旅を通して出会った人から教えてもらったアカデミーに興味をもち、入学することにしたとのことでした。
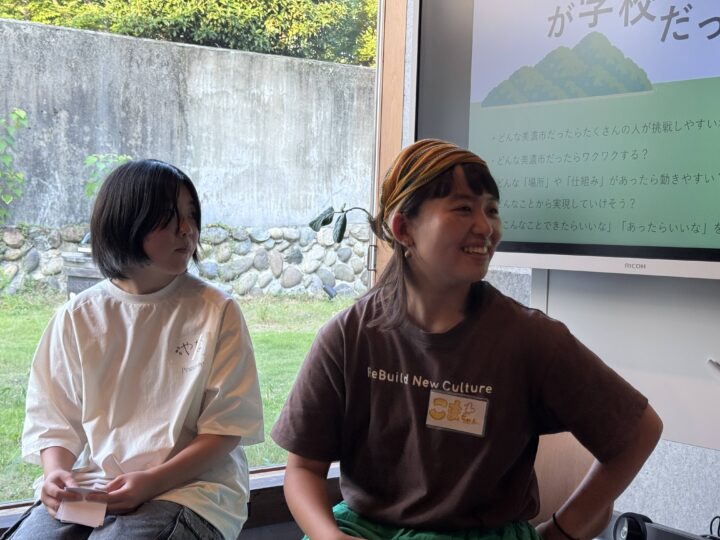
一般的な進路とは異なる道を選んだ、リアル10代の話に、大人たちは熱心に耳を傾けていました。
大人との価値観のギャップに悩みながら、多様な人と交じることで成長していく若者たち。トークセッションの最後、駒田さんの言葉が印象的でした。
「ひとつ言えることは、今幸せだなって思えること。去年、アカデミーに来たときは、どうしようと思ったけど、いろいろな経験をする、いろいろな人と出会うというのを繰り返していって、1年過ごして、まぁ今、幸せって思えるから、それでいいかなって思ってます」
はじめて、ワークショップをデザインする
海士町の報告、そして10代のアカデミー生の話を受けて、美濃市の方々がまちのこれからを考えるディスカッションが行われました。
久野さんからは、「もしも美濃市全体が学校だったら?」というお題が出され、4つのグループに分かれて熱を帯びた声が会場を満たしていきます。
短い時間でしたが、
・人の関心が集まる、”矢印”が集まる場所が昔の学校だった。新しい”矢印が集まる場所”が必要ではないか
・場所は、ハードではなくてもいい。祭りや文化祭のような出来事もあるのでは。
・学校の授業だけではなく、純粋に興味で町に触れる体験があるといい。
・高校もアカデミーも、市外からの通学者が多い。通学より住み込むほうが関係が深まる。
・まちの人、学校、学生、事業者、外の人など、緩やかに混ざる場が必要では。
などなど、たくさんの意見やアイデアが生まれました。
参加者の中には、美濃市教育長の姿も。以前、海士町の取り組みを紹介する書籍を読んで興味を持ち、今回の報告会に参加したとのことでした。そんな教育長からは、人口減少で小学校、中学校が検討されている美濃市で、「これからのこどもたちは、どんな学校なら行きたいか?統合してつくるなら、これまでと違う新しい”普通でない学校”を、美濃市の人々と考えていきたい」という、熱いメッセージが、参加者に伝えられました。

初めてのワークショップ企画に不安もあった久野さんでしたが、結果は大盛況。アカデミーで培った「現地現物」の姿勢とネットワークが、地域と多様な人々をつなぐ場づくりへと活かされました。これからの美濃市の方々とアカデミー生のつながりの広がり、そして久野さんの活動に期待が高まります。頑張ってください!

<森林環境教育専攻 教員 小林(こばけん)>
